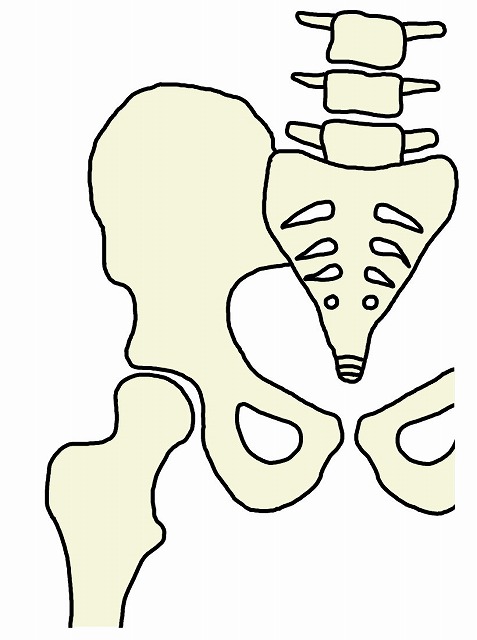大腿骨頸部 骨折 は高齢者に起こりやすいと言われています。大腿骨と言えば身体の上半身を支えており他の骨よりも太くて丈夫なはずです。それが簡単に折れてしまうのはなぜでしょう。これは加齢とともに骨密度が低下し骨粗鬆症となり骨折しやすい状態になるからと言われています。
そして、骨折時は相当な痛みを伴います。完治するには保存的療法もありますが、通常は手術を行って元どおり歩行ができるようになるには長く時間がかかります。できることなら骨折せずに過ごしたいと誰もが思うのではないでしょうか。
大腿骨頸部骨折にならないための知識と対策
- 目次 -
骨密度低下は骨粗鬆症の始まり
骨密度は加齢とともに低下することが知られています。更に、女性は女性ホルモンとの関係で閉経後に骨密度の低下が著明になると言われており、40~50代からは女性のリスクが高くなってきます。従って、骨密度の正常値を維持することが重要です。
骨密度は、YAM(Young Adult Mean)という指標が用いられ、正常値は100%の状態の数値に対して80%以上となっています。70%~80%未満は低下し始めていることを示しており、70%以下になったら要注意です。
骨密度が低下するということは骨粗鬆症に移行し、骨の中の隙間が多くなって海綿状になり、容易に骨折しやすくなるということです。大腿骨のような身体を支える骨が骨折しやすくなったら身体にとって大きな危機です。
骨密度の定期的な測定は健康管理の1つ
骨密度の測定方法は3つあります。
1つ目は、DAX法でX線を使って全身のほとんどの骨の骨密度を測定できます。
2つ目はMD法で、X線を手の骨とアルミニウム版に当て両者の濃度比較で測定するものです。
3つ目は超音波法で、踵と脛に超音波を当てて測定する方法です。簡易的で部位が限定されますが、医療機関以外でも機器を備えている施設なら測定可能です。
従って、日頃から自身の骨の状態を把握し、骨密度低下を早期に発見して骨粗鬆症への対処をすることが大切です。
骨密度が低下し始める40~50代になったら定期的に骨密度を測定することは健康管理の1つです。
骨密度の維持と骨格筋量は関係がある
骨を強くするには骨の成分となるカルシウムを摂るのがいいと言われています。そうすれば骨密度が正常に維持されるはずです。ただ、近年の研究では、骨密度の維持には骨格筋量の増加を進めることが有効であると報告されています。
従って、日頃からカルシウムを含む食品を意識して摂取することと、骨格筋量を増加させるトレーニング(ストレッチや筋トレなど)を併用して行うことがよいと思われます。
高齢者が転倒しやすい原因と“尻もち”の危険性
高齢者は骨粗鬆症の状態に加え、身体機能の低下で歩行障害、筋力の衰えから踏ん張る力やバランスがとれずに転倒することがあげられます。
更に認知症になった場合は、徘徊や危険回避ができず転倒してしまう場合があります。また、糖尿病や甲状腺機能亢進症などの持病がある場合も身体機能に影響し転倒しやすくなると言われています。
そして、転倒時は横転だけでなく、垂直に落ちる“尻もち”も大腿骨頸部に力が加わり骨折に至ってしまうのです。
家の中での転倒が多い
最近は、高齢者が家の中で転倒する事例が多くなってきています。特に、トイレ行動が転倒原因の中で一番多いと言われています。
外出時は、付き添う人がいて、歩行を補助してくれたり車椅子や歩行器を使って安全に移動できます。
一方家の中では、移動距離が短い、場所がわかっている、人手を煩わせたくないという気持ちもあり単独で行動してしまう傾向があります。その結果が転倒、骨折になってしまうのです。
しかし、現代は高齢社会で高齢夫婦の世帯や一人暮らしの世帯もあり、第三者による24時間のモニターができないことが多いです。このことから、家の中で単独行動しても転倒しない対策や転倒してもダメージが少ない対策も考える必要があります。
転倒予防と転倒ダメージが少ない在宅環境の整備
家の中で転倒しない対策としては、バリアフリーの床、手すりの設置などがあげられます。特にトイレは、最後まで自分でしたいという思いを尊重し、できるだけ自分でできるように、いつも居る場所の近くにあることが望ましいと思われます。
転倒してもダメージが少ない対策としては床や壁にクッション性の材質を用いたり、休憩できるソファーを廊下に置くなどがあげられます。
また、介護保険関係ではケアマネージャーに相談し、ディサービスの利用でレクリエーションや機能訓練、入浴介助を受けることができます。
安価に借りられる機器もありますし、設備の費用補助が受けられるものもあります。このように、社会資源も活用して在宅環境を整備することは、転倒の予防と大腿骨頸部骨折を防ぐことにつながると考えます。
まとめ
大腿骨頸部骨折にならないための知識と対策
骨密度低下は骨粗鬆症の始まり
骨密度の定期的な測定は健康管理の1つ
骨密度の維持と骨格筋量は関係がある
高齢者が転倒しやすい原因と“尻もち”の危険性
家の中での転倒が多い
転倒予防と転倒ダメージが少ない在宅環境の整備